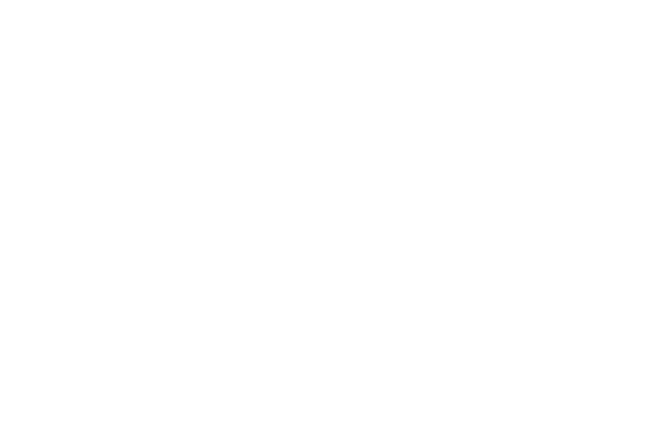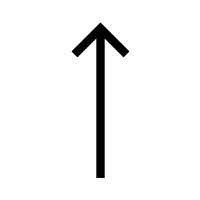はじめに
田んぼは“人工湿地”という自然
田んぼは人の手で水位を調整できる人工の湿地です。用水路から取り入れ、畦で囲い、排水口から外へ戻す――この仕組みがあるからこそ、メダカ・ドジョウ・ゲンゴロウ・カエル・トンボのヤゴなど、水辺を必要とする生き物が暮らせます[1]。
春に水が満ちれば越冬していた生き物が活動を始め、夏は稲の影が涼しい隠れ家に。秋の落水期には水路やため池へと移動していきます。農家の水管理が、そのまま生態系のリズムを形づくっています。
季節ごとの“いのちのカレンダー”
- 春(代かき〜田植え):カエルの卵塊、アメンボ、稚魚の隠れ家
- 初夏(分げつ期):稲の陰が日傘になり、ヤゴやゲンゴロウが活動
- 真夏(出穂期):稲の葉が水面を覆い、魚や昆虫の避暑地に
- 秋(落水期):生き物が水路やため池へ移動し、翌年へ命をつなぐ
畦の草刈りが生み出す環境
畦は小さな草地生態系。草刈りを一度に丸裸にせず、分割して時期をずらして行うと、昆虫や小動物の逃げ場が保たれます。開花中の野草を一部残せば、蜜を求める昆虫が集まり、トンボや鳥もやって来ます[2]。
外来生物 ― スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)
脇山の田んぼでは、スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)が多く生息しています。1980年代に南米から食用として導入され、現在は九州各地に定着した外来種です[3]。
被害の側面
- 稲の幼苗を食害(特に田植え直後)
- 赤紫色の卵を大量に産みつけ、短期間で個体数が増える
活用の側面(無除草剤栽培の一助)
- タニシは雑草の芽や柔らかい草を好んで食べる
- 稲が十分に成長した後は被害が少なく、除草効果を活かせる
- 一部圃場でジャンボタニシを活用した無除草剤栽培を試行・実践
管理の工夫
- 田植え直後は浅水管理で被害軽減
“害”にも“味方”にもなる存在。現場の工夫次第で、環境負荷を抑える栽培パートナーになり得ます[4]。
田んぼは学びの教室(学童稲作)
当地域では、小学校の児童を対象に、JA・自治体・学校が一体となって学童稲作を実施しています。春の田植え、秋の稲刈り、冬の餅つきまで、一年を通じた体験学習です。

「地元小学校での田植え」
- 春:苗を一株ずつ植え、泥に足をとられながら「米づくりの第一歩」を体験
- 秋:稲刈りで収穫の喜びを味わう
- 冬:収穫米で餅つき。地域の人たちと食文化を共有
この取り組みは、米がどのように育ち、食卓へ届くかを五感で学ばせると同時に、田んぼが生き物のすみかであり、地域文化を育む場であることを伝えます。農家・学校・JA・自治体が連携し、地域ぐるみで子どもを育てる仕組みが息づいています[5]。
価格の中に“いのちの価値”を
生き物が豊かな田んぼを維持するには、草刈り・水路整備・水管理・外来種対応など、追加の労力が欠かせません。市場価格には反映されにくいこの見えない労働こそ、農家が日々担っている価値です。私たちの10a=100万円という提案には、「食べものをつくる」だけでなく「いのちの場を守る」という価値も含めたいと考えています。
あわせて読みたい
脚注・出典
- 水田は“人工湿地”として多様な生物の生息・繁殖に寄与します(一般的知見の説明)。地域や管理方法により生物相は変動します。
- 畦の草刈りを帯状に残す・時期分散するなどの工夫は、生息空間の連続性確保に有効とされます(現場実践の知見)。
- スクミリンゴガイ(通称ジャンボタニシ)は南米原産の外来種で、1980年代に食用導入後に各地で定着。稲の幼苗への食害が問題となっています。
- 一方で、雑草の芽・柔らかい草を好む食性を活かし、稲の初期生育を乗り切った後は雑草抑制に寄与させる実践があります(無除草剤栽培の一助)。
- 当地域の学童稲作(田植え・稲刈り・餅つき)は、JA・自治体・学校の連携による年間プログラムとして実施されています(地域実践の紹介)。